― 判例から読み解く創作性ラインと生成AI時代の実務対応 ―
「この写真に著作権はありますか?」
企業の広報担当者、デザイナー、個人クリエイターから、実務で最も多く寄せられる質問の一つです。
特に近年は、スマートフォン写真や生成AIを介在させた画像が増え、「どこからが著作物なのか」が一層分かりにくくなっています。
本稿では、写真の著作物性がどこで決まるのかを、判例の考え方を軸に整理し、生成AI時代における企業・個人クリエイター向けの実務対応まで落とし込みます。
1 写真は原則として「著作物」だが、例外もある
著作権法上、写真は「美術の著作物」に該当し得ます。
しかし、すべての写真が無条件に著作物になるわけではありません。
最高裁を含む一貫した裁判例の立場は、次のとおりです。
写真においても、
被写体の選択、構図、撮影条件、シャッターチャンス等に
撮影者の創作的判断が表れているか
が、著作物性判断の基準となる。
つまり、「写真であること」自体ではなく、
人の創作的関与がどこにあるかが問われます。
2 写真の著作物性を肯定した代表的裁判例
東京地裁平成13年6月21日判決(集合住宅写真事件)
この事件では、不動産広告用に撮影された建物写真について、著作物性が争われました。
裁判所は、
- 建物のどの部分を写すか
- どの角度・距離から撮るか
- 天候や時間帯の選択
といった点に撮影者の判断が介在していることを重視し、
写真の著作物性を肯定しました。
重要なのは、「芸術性が高いか」ではなく、
選択と判断があったかどうかです。
これは、企業実務において極めて重要な視点です。
3 著作物性が否定されたケースもある
一方で、写真であっても著作物性が否定される例は存在します。
東京地裁平成18年3月28日判決(証明写真類似事案)
この事案では、証明写真に近い性質の画像について、
- 撮影方法が定型化されている
- 創作的選択の幅がほとんどない
として、著作物性を否定しました。
この系統の裁判例から導かれるのは、
誰が撮ってもほぼ同じ結果になる写真は、
創作性が否定されやすい
という実務上の経験則です。
4 生成AI画像との共通点と決定的な違い
ここで、生成AI画像との関係が問題になります。
文化庁は、生成AIと著作権の関係について、
「人の創作的寄与が認められない場合、著作物性は否定される」
と整理しています
(文化庁「AIと著作権に関する考え方について(令和5年6月)」)。
この考え方は、写真判例の延長線上にあります。
写真判例が重視してきたのは、
- 人が選んだか
- 人が判断したか
- 人の表現として説明できるか
という点です。
生成AIにおいて、
- 単にプロンプトを1回入力しただけ
- 出力結果をそのまま使用
という場合、
**写真でいう「自動撮影装置に任せたに等しい状態」**と評価される可能性があります。
5 企業実務で実際に起きているトラブル例
企業向け実例(実務上よくあるケース)
企業のマーケティング部門が、
- 生成AIでビジュアルを作成
- 「当社が著作権を保有する前提」で外注先・代理店と契約
しかし後日、
- そもそも著作物性がない可能性
- 著作権譲渡条項が空文化している
ことが法務チェックで発覚。
結果として、
- 契約書の全面見直し
- クライアントへの説明対応
- ブランドリスクの発生
に発展しました。
これは珍しい話ではありません。
6 個人クリエイターが特に注意すべきポイント
個人クリエイターの場合、リスクはさらに顕在化します。
- AI生成画像を「自作」として販売
- 著作権がある前提でライセンス表示
- 二次利用禁止を主張
しかし、創作過程を説明できなければ、
- 著作権侵害の主張ができない
- 逆に不当表示と批判される
という事態になりかねません。
「どう作ったかを言語化できるか」
これが、生成AI時代のクリエイターの最低限の防御線です。
7 実務対応の整理(写真・生成AI共通)
最後に、実務対応を整理します。
① 著作物性は「ある前提」で動かない
写真でもAIでも、原則はフラットに検討する。
② 人の関与を説明できる設計にする
プロンプト、選別、修正、意図を記録する。
③ 契約では著作権依存を減らす
利用許諾型、責任限定条項を活用する。
写真の著作物性を巡る判例は、
そのまま生成AI時代の著作権判断の「地図」になります。
創作性とは、結果ではなくプロセスで決まる。
この視点を持てるかどうかが、
企業・個人クリエイター双方のリスクを分ける分岐点です。

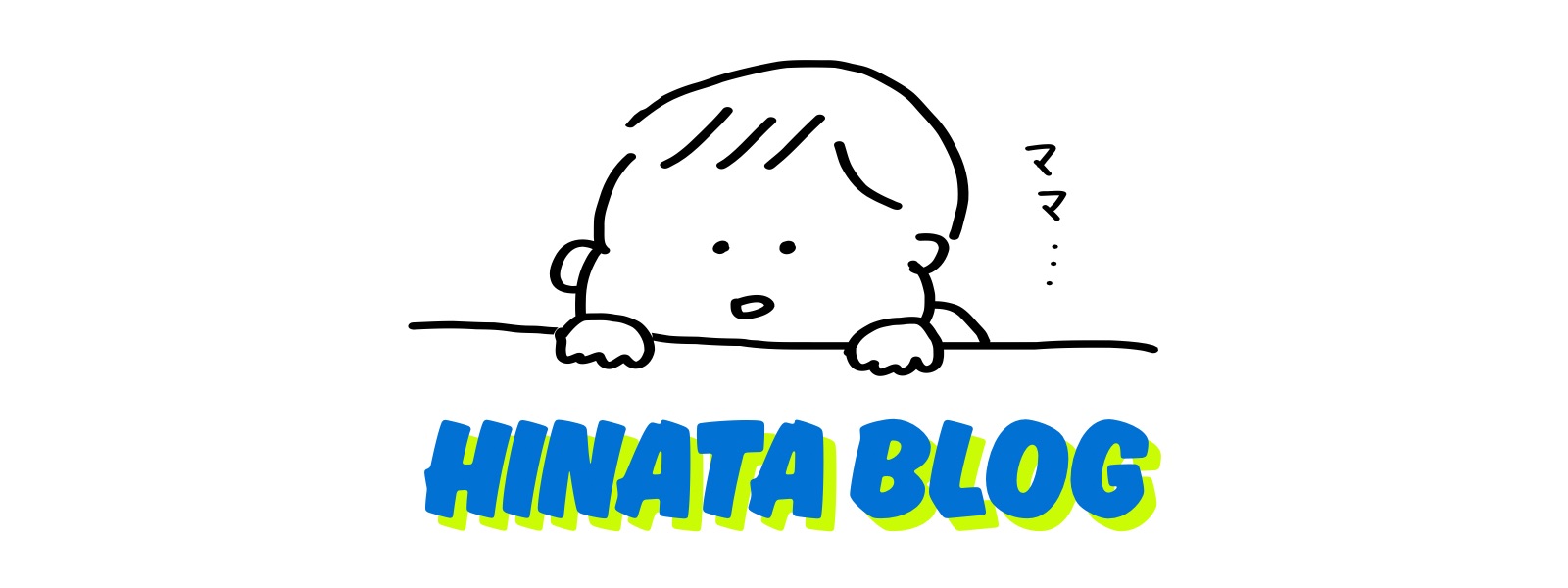


人気記事