― 企業・外注・生成AIが絡むときの著作者判断と実務リスク ―
生成AIを業務に取り入れる企業が増える中で、実務上もっとも混乱が生じやすいのが
「結局、誰が著作者なのか?」
という問題です。
制作に関与する主体が、
- 企業(発注者)
- 外注先(制作会社・個人)
- 生成AI
と複数存在する場合、著作者の帰属を誤ると、権利行使ができない/契約が空文化するといった深刻なリスクが生じます。
本稿では、判例と従来の著作権理論をベースに、生成AI時代の著作者判断を実務的に整理します。
1 大原則:「著作者=創作した人」
著作権法上の大原則は極めてシンプルです。
著作者とは、著作物を創作した者である
企業名義でも、契約書でもなく、
**実際に創作的表現を行った「人」**が基準になります。
これは生成AIが絡んでも変わりません。
2 企業が著作者になるケース(職務著作)
まず、企業実務で頻出するのが職務著作です。
著作権法15条(職務著作)
以下の要件を満たす場合、法人が著作者になります。
- 法人の発意に基づくこと
- 法人の業務に従事する者が作成したこと
- 職務上作成されたこと
- 就業規則等に別段の定めがないこと
たとえば、
- 社内デザイナーが業務としてAIを使い制作
- 企画・指示・選別がすべて社内で完結
という場合、企業著作者が成立する余地があります。
ただし重要なのは、
👉 「人の創作的寄与」が前提
という点です。
AIがほぼ自動で出力し、人の創作性が認められなければ、
そもそも「著作者」という議論自体が成立しません。
3 外注制作の場合:著作者は原則「外注先」
次に多いのが、制作を外部に委託するケースです。
原則ルール
- 外注先が創作した
→ 外注先が著作者
これは、生成AIを使っていても変わりません。
「お金を払ったから」「指示を出したから」
という理由だけで、著作者が発注者に移ることはありません。
4 契約でよくある誤解:「著作権譲渡=著作者?」
実務で非常によくある誤解がこれです。
「著作権譲渡契約があるから、著作者は企業」
これは誤りです。
- 著作者:創作した人
- 著作権者:権利を持つ人
は別概念です。
生成AI案件ではさらに厄介で、
- そもそも著作物性がない
- 譲渡対象の著作権が存在しない
というケースも珍しくありません。
この場合、
- 著作権譲渡条項は空文化
- 契約リスクだけが残る
という結果になります。
5 生成AIが関与した場合の著作者判断
では、生成AIを使った場合、著作者は誰になるのでしょうか。
① AIは著作者にならない
現行法上、AIは著作者になりません。
著作者になれるのは「人」に限られます。
② 判断軸は「誰の創作か」
ポイントは一つです。
創作的表現を行ったのは誰か
- プロンプト設計
- 試行錯誤
- 出力結果の選別
- 修正・加工
これらを主導した「人」が、著作者候補になります。
6 実務で問題になるグレーケース
ケース1:企業が指示、外注がAI操作
- 企業:ざっくりした指示
- 外注:プロンプト設計・選別を主導
→ 外注先著作者の可能性が高い
ケース2:外注は操作のみ、企業が全判断
- 企業が詳細なプロンプト設計
- 出力結果の選択・修正も企業
→ 企業側に著作者性が認められる余地
ケース3:ほぼ自動生成
- テンプレプロンプト
- 自動生成→即使用
→ 著作物性自体が否定される可能性
7 判例思考で考える「誰が創作したか」
生成AI直接の判例はまだ少ないものの、
裁判所は一貫して、
- 誰が表現を決定したか
- 誰の判断が結果に反映されているか
を見ています。
これは、
- ゴーストライター事件
- デザイン外注事件
- 写真著作物性判例
すべてに共通する考え方です。
生成AIは、
判断主体を見えにくくするだけで、
判断基準そのものを変えるものではありません。
8 企業・クリエイター向け実務対応まとめ
① 著作者を「契約で作れる」と思わない
創作実態が最優先。
② 創作プロセスを可視化する
誰が何を判断したかを記録。
③ 契約は著作者前提にしすぎない
利用許諾型・責任分配型へ。
生成AI時代の著作者判断は、
「誰がボタンを押したか」ではなく、
**「誰が表現を決めたか」**で決まります。
この視点を持たずに契約や運用をすると、
権利のないコンテンツを、権利がある前提で使う
という最悪の事故が起こり得ます。
次回は、
第4回|「企業は生成AIコンテンツをどう使えば安全か?」(利用・契約設計編)
へ進みます。

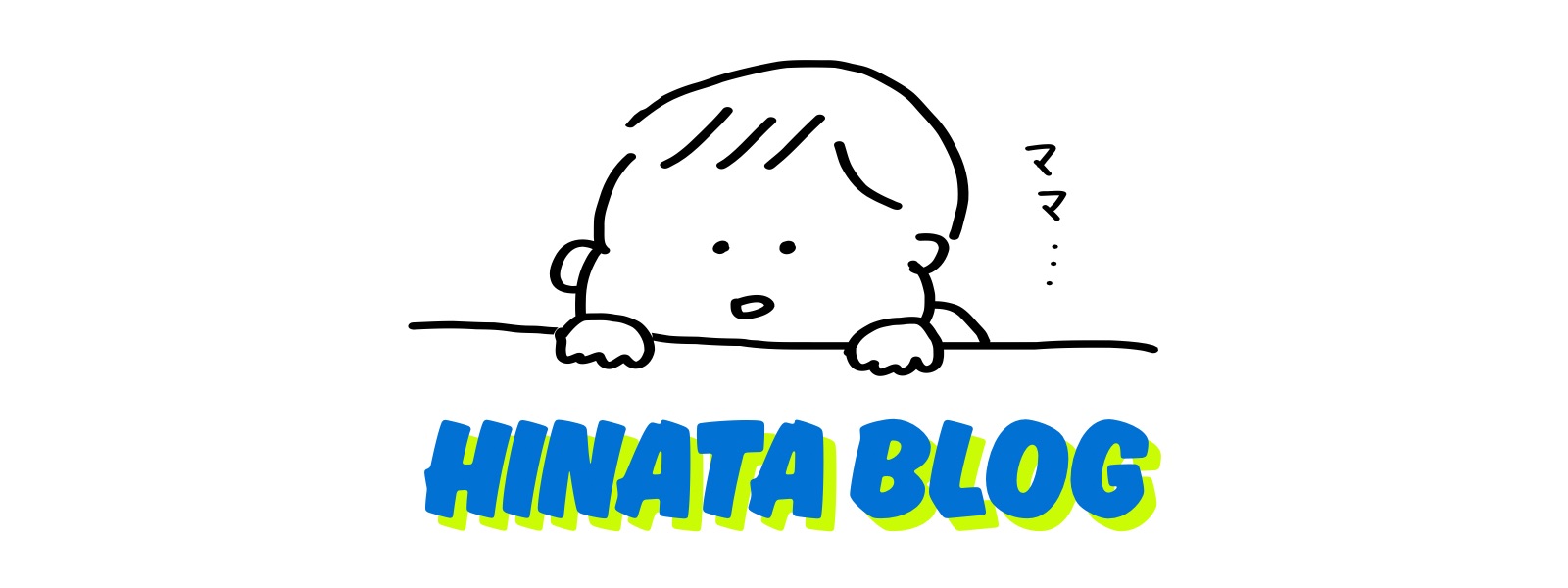


人気記事